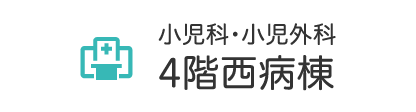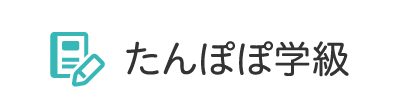小児科ブログ
浜松医科大学小児科学講座 開講50周年
2025/10/03
2025年9月 浜松医科大学小児科学講座 開講50周年の記念式典が開催されました。
6月にご逝去された初代教授五十嵐良雄先生が50周年記念誌に寄せられたお話によりますと、昭和50年(1975年)4月に五十嵐先生が就任され、昭和53年11月外来診療開始、昭和54年病院東5階に小児科入院病棟が開かれたそうです。昭和55年には1期生が卒業し、卒業したばかりの小児科医が誕生しました。50年間に五十嵐教授、大関武彦教授、緒方勤教授、宮入烈教授をはじめ、多くの先輩の先生方にご指導を受けた浜松医科大学小児科同門の医師は、260人を数えるそうです。
浜松医科大学小児科学講座50周年は、小児科学講座の歴史とともに、時代の変化や医学・医療の進歩、また医師としての個人の人生に思いを馳せるとても貴重な機会を与えてくれました。研修医時代(当時は卒後すぐに専門研修)に苦楽をともにした先生方と久しぶりにお会いし、当時の記憶が懐かしく蘇りました。
私が浜松医科大学小児科学講座の一員となった平成元年(1989年)は、まだまだ講座の医師の数は少なく、先輩の先生方はとても若い頃から関連病院小児科の医長として赴任され、ご苦労があったのではないかと思います。2025年現在は、多くの小児科の指導医やサブスペシャルティー領域の指導医がそろい、恵まれた研修プログラムやカリキュラムが提供されています。
女性医師を取り巻く環境も大きく変りました。わが国の医学部の女性比率は、1985年には13.0%、2024年の医学部入学者全体の女性比率は過去最高の40.2%であったそうです。
1985年当時、卒後医師を一生の仕事としない女性も少なくなかったと思いますが、その分、女性差別のリスクをはらむ社会構造であったと思います。現在では、人口減少や働き方改革の影響もあり、医学部卒業生は、男女関係なく、医師・研究者などとしての職業を全うすることが当然のように期待されています。私自身は、平成初期においても医師として女性差別を受けた経験はありませんでした。小児科にはGENDERについて古くから成熟した環境があったのではないかと思います。現在は真の意味でglass ceilingがほぼなくなり、女性医師支援センターによる支援も充実しています。
50年間の医学・医療の進歩については枚挙にいとまがありません。私の小児科サブスペシャルティー領域(小児神経・先天代謝異常症・臨床遺伝)を例にあげますと、単一遺伝子疾患を診療対象とすることも多いため、診断では遺伝子・ゲノム解析の恩恵を多大に受けるようになりました。治療では、以前は、神経疾患は治療不能と考えられていましたが、脊髄性筋萎縮症、Duchenne型筋ジストロフィーをはじめ、疾患遺伝子に対する核酸医療、遺伝子治療や酵素補充療法が可能となった疾患が多くなり、確実な早期診断と治療開始が求められるようになりました。小児神経の領域では、てんかんや知的発達症や自閉スペクトラム症などの神経発達症の患者さんの診療も担います。ひとことで神経発達症といっても、基礎にもつ病態は様々ですので、疾患修飾療法を行う必要がある場合があることに留意しながら診療を行う必要性が高まっています。この領域では、リハビリ、家庭、学校、行政、福祉との連携が重要であることは、以前も現在も変わっていませんが、医療的ケア児や発達障害に対する支援が充実してきています。
浜松医科大学小児科学講座50周年をきっかけに、小児科学講座の歴史とともに、時代の変化や医学・医療の進歩について振り返りました。小児科医療の集約化などが求められる昨今であり、時代に即した小児医療のあり方や小児科医像は、これからも変遷し続けると思いますが、多くの仲間とともに、小児の新しいことに挑戦し続ける小児科学講座であり続けることと思います。
6月にご逝去された初代教授五十嵐良雄先生が50周年記念誌に寄せられたお話によりますと、昭和50年(1975年)4月に五十嵐先生が就任され、昭和53年11月外来診療開始、昭和54年病院東5階に小児科入院病棟が開かれたそうです。昭和55年には1期生が卒業し、卒業したばかりの小児科医が誕生しました。50年間に五十嵐教授、大関武彦教授、緒方勤教授、宮入烈教授をはじめ、多くの先輩の先生方にご指導を受けた浜松医科大学小児科同門の医師は、260人を数えるそうです。
浜松医科大学小児科学講座50周年は、小児科学講座の歴史とともに、時代の変化や医学・医療の進歩、また医師としての個人の人生に思いを馳せるとても貴重な機会を与えてくれました。研修医時代(当時は卒後すぐに専門研修)に苦楽をともにした先生方と久しぶりにお会いし、当時の記憶が懐かしく蘇りました。
私が浜松医科大学小児科学講座の一員となった平成元年(1989年)は、まだまだ講座の医師の数は少なく、先輩の先生方はとても若い頃から関連病院小児科の医長として赴任され、ご苦労があったのではないかと思います。2025年現在は、多くの小児科の指導医やサブスペシャルティー領域の指導医がそろい、恵まれた研修プログラムやカリキュラムが提供されています。
女性医師を取り巻く環境も大きく変りました。わが国の医学部の女性比率は、1985年には13.0%、2024年の医学部入学者全体の女性比率は過去最高の40.2%であったそうです。
1985年当時、卒後医師を一生の仕事としない女性も少なくなかったと思いますが、その分、女性差別のリスクをはらむ社会構造であったと思います。現在では、人口減少や働き方改革の影響もあり、医学部卒業生は、男女関係なく、医師・研究者などとしての職業を全うすることが当然のように期待されています。私自身は、平成初期においても医師として女性差別を受けた経験はありませんでした。小児科にはGENDERについて古くから成熟した環境があったのではないかと思います。現在は真の意味でglass ceilingがほぼなくなり、女性医師支援センターによる支援も充実しています。
50年間の医学・医療の進歩については枚挙にいとまがありません。私の小児科サブスペシャルティー領域(小児神経・先天代謝異常症・臨床遺伝)を例にあげますと、単一遺伝子疾患を診療対象とすることも多いため、診断では遺伝子・ゲノム解析の恩恵を多大に受けるようになりました。治療では、以前は、神経疾患は治療不能と考えられていましたが、脊髄性筋萎縮症、Duchenne型筋ジストロフィーをはじめ、疾患遺伝子に対する核酸医療、遺伝子治療や酵素補充療法が可能となった疾患が多くなり、確実な早期診断と治療開始が求められるようになりました。小児神経の領域では、てんかんや知的発達症や自閉スペクトラム症などの神経発達症の患者さんの診療も担います。ひとことで神経発達症といっても、基礎にもつ病態は様々ですので、疾患修飾療法を行う必要がある場合があることに留意しながら診療を行う必要性が高まっています。この領域では、リハビリ、家庭、学校、行政、福祉との連携が重要であることは、以前も現在も変わっていませんが、医療的ケア児や発達障害に対する支援が充実してきています。
浜松医科大学小児科学講座50周年をきっかけに、小児科学講座の歴史とともに、時代の変化や医学・医療の進歩について振り返りました。小児科医療の集約化などが求められる昨今であり、時代に即した小児医療のあり方や小児科医像は、これからも変遷し続けると思いますが、多くの仲間とともに、小児の新しいことに挑戦し続ける小児科学講座であり続けることと思います。
小児科学講座 福田冬季子