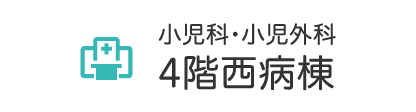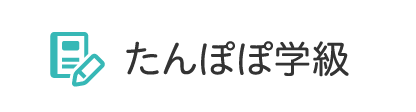小児科ブログ
科研費、四季のこころ
2025/11/14
春は支度 夏は書く 秋は寝て待つ 冬は果報 作:瀬少納言
2013年卒業の瀬川です。今回、科研費(科学研究費助成事業・日本学術振興会)をテーマにブログ原稿を書く機会をいただきました。正直に言えば、私のような若手が科研費について語るのは畏れ多く、恐縮の念を禁じ得ません。
私は令和7年度の科研費(基盤研究C)に採択されました。研究内容は、新生児呼吸障害の早期発見方法の開発に関するもので、現在その研究を進めています。今回の科研費は私個人の力というよりも、共同研究者の生殖周産期医学講座の宗先生や飯嶋先生をはじめとする新生児グループの先生方、学内アドバイスサービスで添削・助言をくださった多くの先生方のご協力のもとで採択されたものです。ここでは、若手として科研費に挑戦した経験を、後輩の皆さんへお伝えできればと思います。
科研費とは何か
私は恥ずかしながら、3年前までは科研費についてぼんやりとしか理解しておらず、ある先生に「何のために必要なのですか?」と尋ねてしまったほどです。そんな私で恐縮ですが、今から少し偉そうに書きます。
科研費は、人文学、社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」(研究者の自由な発想に基づく研究)を格段に発展させることを目的とする「競争的研究費」であり、ピアレビューにより、豊かな社会発展の基盤となる独創的かつ先駆的な研究を助成する制度です(科研費HPより引用)。
大学に所属する医師にとっては、研究を進めるための基盤そのものであり、「研究をするなら避けて通れない制度」といえます。例えば、試薬や解析にかかる研究費、学会発表や論文投稿のための費用など、外部資金なしには前に進めません。そのため、科研費への応募は実質的に「研究者の義務」に近いと感じています。
科研費に関して無知だった私がまず取り組んだのは、情報収集でした。科研費に関する書籍は多数出版されていますので、そのうち2冊を購入し熟読しました。また、院内で開催される「研究計画調書の書き方セミナー」などに参加し、実際に研究計画調書の採点を担当されている先生から講義を受けることで、採択されやすい研究計画調書の傾向を学ぶことができました。
1年目は不採択。2年目にリベンジ
1年目の申請は不採択でした。それなりに仕上がっていたと思っていたため、正直落胆しました。本学には、不採択の研究計画調書を添削してもらえるアドバイスサービスがあり、「内容は悪くないが、メッセージが伝わりにくい」とご指摘をいただきました。また、取り掛かり始めたのが夏前と遅く、十分な推敲ができていなかった点も敗因だったと思います。
2年目は同じテーマで再挑戦しました。内容を大きく変えたわけではなく、ご指導いただいた先生方の助言のもと、より分かりやすく、伝わりやすい形へと修正しました。また、前年度の反省も踏まえ、早めの準備を心掛け、5月頃から共同研究者の先生と作戦を練り始めました。7月中旬に公募が始まるため、募集要項に沿った内容で書き直しました。実際に執筆したのは約2か月間でしたが、前年度の内容を基にブラッシュアップしたため、比較的短期間で仕上げることができました。締め切りが9月初めですが、事前にアドバイスサービスに申し込むため、8月中旬には完成を目指しました。7月、8月は研究計画調書と向き合う日々を過ごしました。
研究計画調書の作成で意識したこと
・自身の研究について深く知る
研究計画調書を書く前に、自身の研究内容をどれだけ理解しているかが重要だと感じました。そのため、他者へのプレゼンテーションを通して理解を深めました。
ご存じの先生もいらっしゃると思いますが、本学に「やらまいかピッチ」という、自身の研究をスライドで発表するイベントがあります。実際に発表しましたが、評価は振るいませんでした。ただ、スライド作成を通じて研究内容の理解が深まり、どのような図表を提示すれば関心を引き、理解を促せるのかを学べたことは大きな収穫でした。科研費の研究計画調書でも、その時に使用した図を一部採用しており、その項目は高く評価されたようです。
・第一印象が大事
科研費の研究計画調書は、医学的に正しいだけでは採択されないようです。さまざまな書籍に書かれていますが、「専門外の審査員が読んでも、その研究の価値が伝わるか」が重要です。審査員の先生からも、「パッと見て読みたくなる研究計画調書かどうかを意識している」と伺いました。そのため、1枚目のページには図やイラストを載せ、審査員の目を引く工夫をしました。
・文章のブラッシュアップにはAIツールが有用
「てにをは」の校閲にとどまらず、メッセージをどう強調すればよいか、どんな表現が自然かなどを提案してくれます。私は国語が苦手なので、毎日のようにAIツールとやり取りしながら文章を磨きました。また、有料版にすると使える機能の幅が広がるため、より効果的に活用できます。
最後に
科研費を通じて、周囲の支えの大きさを改めて感じました。宗先生、飯嶋先生、新生児グループの先生方、また研究計画調書の添削や助言をくださった先生方に、心より感謝申し上げます。ご多忙の中、貴重なお時間を割いてくださったことが、今回の結果につながったのだと思います。
私自身も、まだまだ学びの途中です。これからも、支度を怠らず、書く手を止めず、次の果報につなげていきたいと思います。
小児科学講座 瀬川祐貴